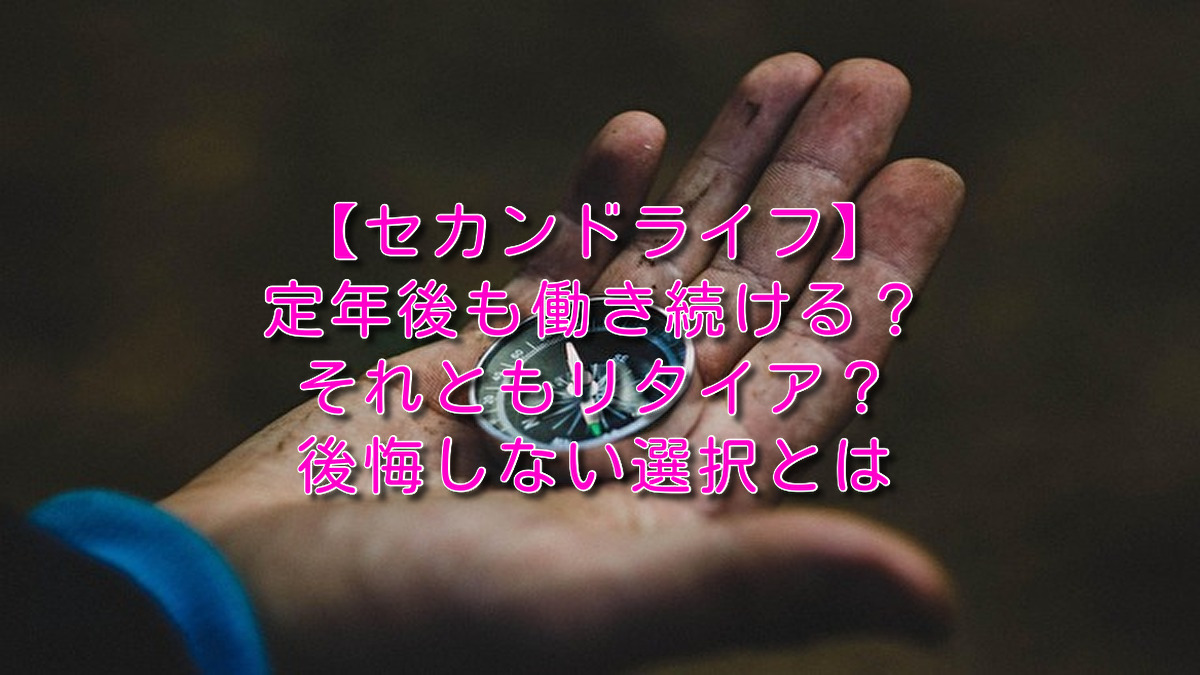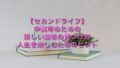「定年後、どうする?」――これは多くの人が50代後半になると意識し始めるテーマです。
長年勤めた会社を60歳で一区切りとするのか、再雇用で65歳まで働くのか、それとも思い切って早めにリタイアするのか。どの選択にも「正解」はありませんが、「後悔しない選択」はあります。
ある60歳の男性はこう話してくれました。
「あと5年は働けると言われたけど、体力よりも気力が持つかどうか悩んでいる」
一方で、早期退職した知人の中には「やりたいことがあると思って辞めたのに、いざ時間ができたら何をすればいいかわからなかった」と戸惑う人もいます。
人生100年時代。定年後の20年、30年をどう過ごすかは、まさに「第2の人生の設計」です。今回は「働き続ける」「リタイアする」それぞれの選択肢を多面的に整理し、自分らしい答えを導くヒントをお伝えします。
働き続ける理由とメリット
① 経済的な安心感
公的年金の受給開始が65歳以降となった現在、60歳でリタイアすると「収入がない期間」が生まれます。再雇用や転職により働き続けることで、年金受給までの“つなぎ期間”を補うことができます。
実際、厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、60歳以降も働く理由のトップは「生活の安定のため」が過半数を占めています。
たとえば、再雇用で年収が現役時代の半分になっても、生活費をまかなえるだけの収入があることで心理的な余裕が生まれます。
「収入が減っても、まだ稼げるという安心感が気持ちを前向きにしてくれた」
と語る人も多いのです。
② 社会とのつながり
仕事を通じて得られるのはお金だけではありません。人との関わりや、誰かに必要とされる感覚も大きなモチベーションになります。
特に長年会社に勤めてきた人ほど、退職後の「人との接点の減少」に寂しさを感じやすいもの。地域のボランティア活動やNPOなど、報酬を得ない「働く形」も選択肢のひとつです。
例えば、ある元営業職の男性(62歳)は定年後、地域の子ども食堂の運営を手伝うようになり、
「数字ではなく笑顔で成果を感じる仕事に出会えた」
と話します。働き方の形を変えても、「社会との関わり」は生涯続ける価値があります。
③ 健康維持と生きがい
適度に働くことは、心身の健康を保つ上でも効果的です。
リタイア後に急に家にいる時間が増えると、生活リズムが崩れたり、運動量が減ったりして体調を崩すケースもあります。
日本老年学的評価研究によると、60歳以降も社会的役割を持つ人の方が、要介護リスクが低いというデータもあります。
リタイアを選ぶ理由とメリット
① 自由な時間の獲得
長年「仕事中心」で走り続けてきた人にとって、リタイアは“自分の時間を取り戻す”チャンスです。
「これまで家族に迷惑をかけた分、夫婦で旅行したい」「趣味に没頭したい」など、心身のリフレッシュを目的とする人も少なくありません。
たとえば、早期退職した男性(58歳)は、長年の夢だった日本一周キャンピングカーの旅を実現。
「仕事では味わえなかった自由を手に入れた」と笑顔で語ります。
リタイア後の時間を“消費”ではなく“投資”に変えることで、人生の満足度は大きく変わります。
② ストレスからの解放
会社という組織の中では、どうしても上下関係や人間関係のストレスがつきものです。
その環境から離れることで、心の健康を取り戻す人もいます。
特に管理職や責任ある立場を長年務めた方ほど、「心の疲労」が蓄積しているもの。
「これ以上ストレスを抱えるよりも、自分を取り戻す時間を優先したい」という選択は、決して逃げではありません。
③ 新しい挑戦のスタート
リタイアは“終わり”ではなく“始まり”です。
時間と自由を得た今こそ、第二のキャリアやライフワークに挑戦するチャンスでもあります。
最近では、退職後に小規模な起業をする人も増えています。総務省の「起業実態調査」によると、60歳以上の起業家は全体の約20%を占めており、「経験」と「人脈」を活かしたスモールビジネスが人気です。
たとえば、自宅の一部を使ったレンタルスペース、ネット販売、地域での講師活動など、リスクを抑えた働き方が可能です。
働き続けるかリタイアか ― 判断のポイント
どちらを選ぶにしても、最も大切なのは「自分の価値観に合った選択をすること」です。
① 経済的基盤の確認
リタイアを考える前に、まず「生活費」と「老後資金」をシミュレーションしておくことが重要です。
・毎月の生活費はいくらか
・年金や退職金の見込み
・医療費や介護費の備え
金融庁の「老後資金シミュレーター」や日本年金機構の「ねんきんネット」を活用すれば、簡単に将来の受給額を確認できます。
現実的な数字を把握した上で、「あといくら稼ぐ必要があるのか」「どの程度の支出なら安心できるのか」を明確にしましょう。
② 心身の健康状態
「働きたいけど体がついていかない」「もう少し休みたい」など、心と体の状態は個人差があります。
一度、健康診断やストレスチェックを受けて、働くかリタイアするかの判断材料にするのも良い方法です。
特に60歳前後では、体力や集中力の変化を感じやすい時期。無理をせず「長く続けられるペース」を意識しましょう。
③ 家族との対話
定年後の生活は、本人だけでなく家族にも影響します。
配偶者が「もっと一緒に過ごしたい」と思っているのか、「自分の時間を大切にしたい」と考えているのか。
それを共有せずにリタイアや再雇用を決めると、あとで「こんなはずじゃなかった」とズレが生じることも。
夫婦で「お金」「健康」「時間」の3つをテーマに話し合うことが、後悔しない選択への第一歩です。
公的情報源を活用して判断材料を増やそう
将来の生活設計を考えるうえで、信頼できる情報源を参考にすることが大切です。
- 日本年金機構『ねんきんネット』
自分の年金記録や将来の受給見込みをシミュレーション可能。
https://www.nenkin.go.jp/ - 厚生労働省『生涯現役促進地域連携事業』
定年後の再就職・地域活動支援など、働き続けたい人向けの制度を紹介。
https://www.mhlw.go.jp/ - 中小企業庁『起業支援ポータル』
シニア世代の起業支援制度・事例を掲載。
https://j-net21.smrj.go.jp/ - 金融庁『老後の生活設計ガイド』
資金計画やリタイア後の資産運用に関する基礎情報がまとまっています。
https://www.fsa.go.jp/
まとめ:働くか、リタイアか。その答えは「今の自分」に聞く
定年後の選択に“正解”はありません。
重要なのは、「何を優先したいか」を明確にすることです。
もし経済的な安心を重視するなら、再雇用や週数日の仕事を続ける選択も良いでしょう。
一方で、心と体をリセットして新しい人生に挑みたいなら、早期リタイアも立派な決断です。
働くこと=生きることを支える手段
リタイアすること=生き方を再構築する機会
どちらの道も「自分で選ぶ」ことが、最大の価値です。
焦らず、比較し、考え、対話することで、きっとあなたにとっての“後悔しない選択”が見つかるはずです。