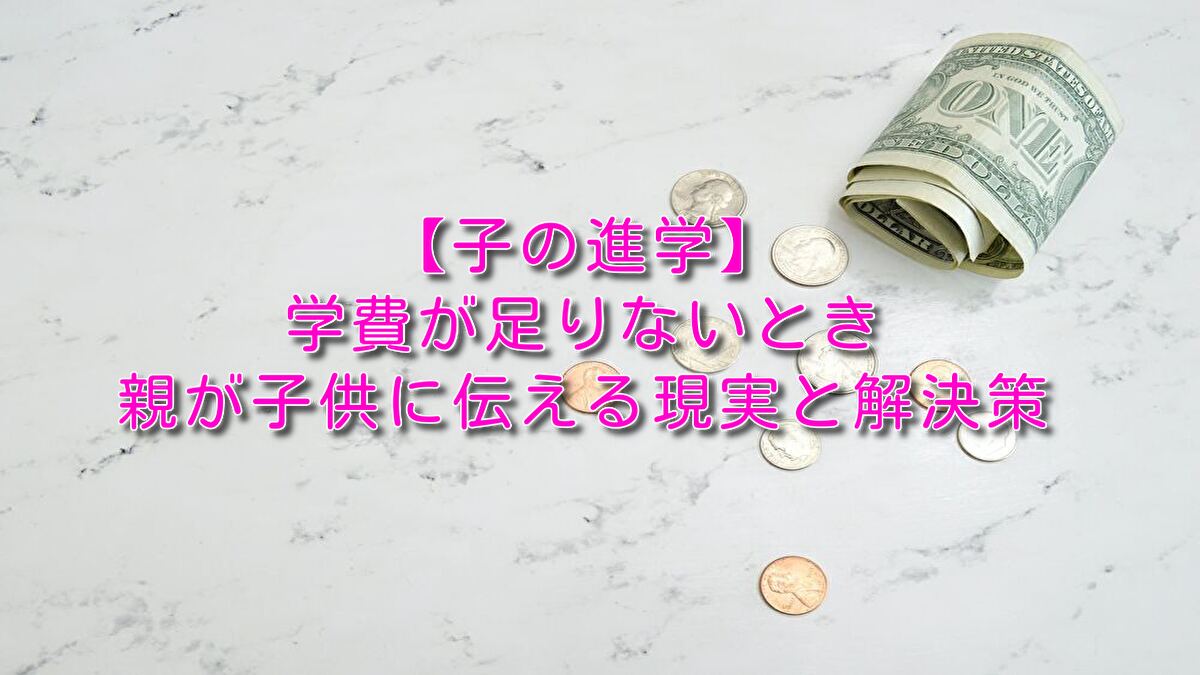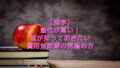子供の進学は親にとって大きな喜びである一方、同時に「学費」という現実的な課題に直面します。特に大学進学では、授業料・生活費・受験関連費用と多岐にわたり、世帯によっては家計に大きな負担となります。十分な貯蓄があれば問題は少ないですが、そうでない場合、親としてどう子供に伝え、どう解決策を探るべきか。本記事では、親世代に向けて具体的な視点と実践的な解決策を整理していきます。
1.進学費用の現実を知る
まず押さえておきたいのは、大学進学にかかる費用の全体像です。文部科学省の調査によると、国公立大学の学費は授業料だけで年間約54万円、私立大学では文系で約90万円、理系では120万円前後が目安です。加えて、入学金や施設費、教科書代などの初期費用も必要です。さらに、下宿を伴う場合には生活費が年間100万円以上かかるケースも珍しくありません。
例えば、ある家庭では「自宅から通える私立大学なら何とかなるだろう」と考えていたものの、実際は初年度に入学金や設備費で100万円以上を一括納入する必要があり、貯蓄が一気に減少しました。親としては予想以上の負担感に驚かされたそうです。このように、学費は“分割で払えるもの”と“初年度にまとめて必要なもの”があるため、全体像を早めに把握することが不可欠です。
2.親が子供に伝えるべき「現実」
学費が足りないとき、多くの親は「子供に心配をかけたくない」と考えがちです。しかし、現実を正しく伝えないと、子供は自分の進路選択が家庭の負担になっていることに気付けません。
例えば、ある家庭では「学費は何とかなるから気にせず志望校を選びなさい」と伝えていたものの、実際には奨学金と教育ローンに大きく依存することになり、子供が社会人になってから返済負担で苦労しました。結果的に「もっと早く現実を教えてほしかった」と親子の間にわだかまりが残ったといいます。
親としては、「希望を尊重しながらも、家計に無理がある場合は率直に伝える」ことが大切です。具体的には、
- 家計の現状(貯蓄・収入・借入の可否)
- 支払い可能な範囲
- 奨学金やバイトを組み合わせる必要性
を整理して話し合うことが必要です。これは「夢をあきらめさせるため」ではなく、「現実的な選択肢を一緒に探すため」の対話です。
3.学費不足を補う手段
進学費用が足りないとき、どのような解決策があるのでしょうか。主な手段を整理します。
(1)奨学金制度の活用
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金は代表的な制度です。無利子(第一種)、利子あり(第二種)があり、世帯収入に応じて利用可能です。加えて、自治体や民間財団が独自に奨学金を設けている場合もあります。
例えば、東京都のある家庭では、第一種奨学金と地方自治体の給付型奨学金を組み合わせ、実質的に年間40万円近い支援を受けることができました。調べれば意外と活用できる制度は多いのです。
(1)-1 奨学金を利用する際の注意点
奨学金は進学費用を補う大きな支えになりますが、同時に「将来返済しなければならない借金」であることを忘れてはいけません。最近の報道でも、奨学金返済が長期間にわたり生活を圧迫するケースが多く取り上げられています。
主な注意点
- 返済総額を把握すること
月々の返済額だけを見ると「数万円程度なら大丈夫」と思いがちですが、10年〜20年単位で返済が続き、総額では数百万円になることもあります。 - 利息負担に注意
第二種奨学金(利子あり)は金利が上限3%と定められており、長期返済では利息分が大きく膨らむ可能性があります。 - 就職後の返済リスク
就職が思うようにいかない、収入が安定しないなどの状況では、毎月の返済が大きな負担になります。返済が滞ると信用情報に影響し、クレジットカードや住宅ローンが利用できなくなる場合もあります。 - 親子での役割分担を確認する
返済は原則として本人ですが、実際には親が援助するケースもあります。最初から「誰がどこまで負担するか」を話し合っておくとトラブルを避けられます。
事例
例えば、ある学生は私立大学進学のために第二種奨学金を毎月10万円借りました。卒業時点で借入総額は約480万円。就職後、月2.5万円の返済が20年間続くことになり、社会人生活の大きな制約となっています。「もう少し返済額をイメージできていれば、進学先の選択も変わっていた」と本人は振り返ります。
(2)教育ローンの利用
日本政策金融公庫の「国の教育ローン」は、世帯年収に制限があるものの、低金利で最大450万円まで借りられます。銀行や信用金庫の教育ローンも選択肢です。注意点は返済期間と返済開始時期。家計の将来設計に影響するため、無理のない返済計画を立てることが不可欠です。
(3)アルバイトや進学先の工夫
子供自身がアルバイトで生活費の一部を賄うのも現実的な方法です。もちろん学業優先が前提ですが、「週2回、月3万円」程度でも年間30万円以上となり、学費の一部をカバーできます。
また、自宅から通える大学を優先する、私立理系ではなく国公立を目指すなど、進学先の選択を工夫することで大きく費用を抑えられます。
4.親の家計に与える影響と長期的視点
進学費用を準備する際には、親自身の老後資金とのバランスを考えることも大切です。無理に教育費を優先しすぎて老後資金が不足すれば、結局は子供に負担をかけてしまうことになりかねません。
例えば、ある家庭では教育ローンを無理に借りて子供を私立大学に進学させましたが、その後親が定年退職を迎えた際、老後資金が不足し、結果的に子供が仕送りを続けることになりました。親子ともに苦しい状況となり、進学時の判断を悔やんだといいます。
進学費用の不足は「親子での共同課題」として捉えるべきです。親の老後・子供の将来をともに考えながら、持続可能な選択を目指すことが最も大切です。
5.親子での話し合いをどう進めるか
学費について子供と話すときは、単なる「お金が足りない」というネガティブな話に終わらせないことが重要です。以下の手順が参考になります。
- 現状共有:家計の状況をわかりやすく説明する(貯蓄額や支出の内訳を簡単に示す)。
- 希望確認:子供が行きたい大学や学びたい分野を尊重する。
- 選択肢検討:奨学金・教育ローン・バイト・自宅通学などの具体策を一緒に考える。
- 合意形成:どの進路が現実的かを親子で納得感を持って決める。
あるご家庭では、高3の夏休みに親子で「進学費用会議」を開き、模擬家計簿を使って学費シミュレーションを行いました。その結果、子供が「学費を親に全額頼るのは難しい」と理解し、自分から奨学金を調べ始めたそうです。こうした話し合いは、子供にとっても金融リテラシーを学ぶ良い機会になります。
6.まとめ|「現実」と「可能性」を両立させる
学費不足という課題は、決して珍しいものではありません。むしろ、多くの家庭が同じ悩みを抱えています。大切なのは、親が一人で抱え込むのではなく、子供と現実を共有し、一緒に解決策を模索することです。
奨学金や教育ローンなどの制度を活用すれば、進学の可能性を広げることは十分に可能です。また、子供が自分で費用の一部を担うことも、将来に向けた大きな成長の機会となります。
「現実を直視すること」と「子供の可能性を支えること」は矛盾しません。むしろ両立させることこそが、親として最も重要な役割といえるでしょう。